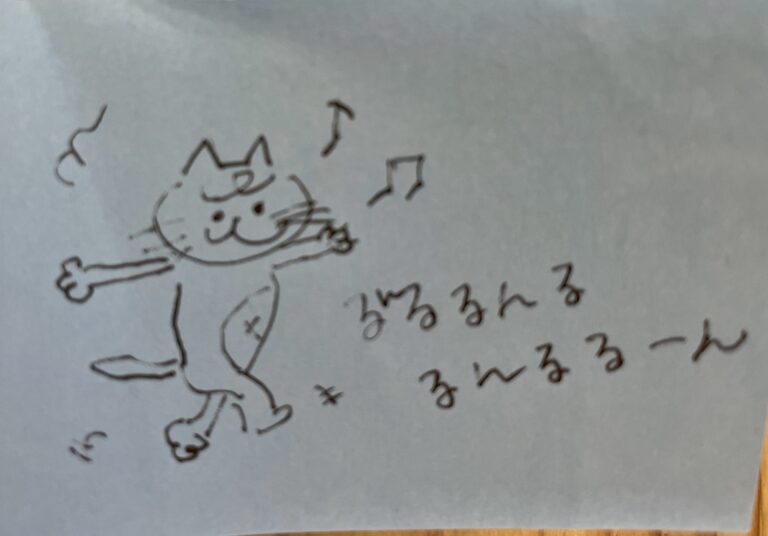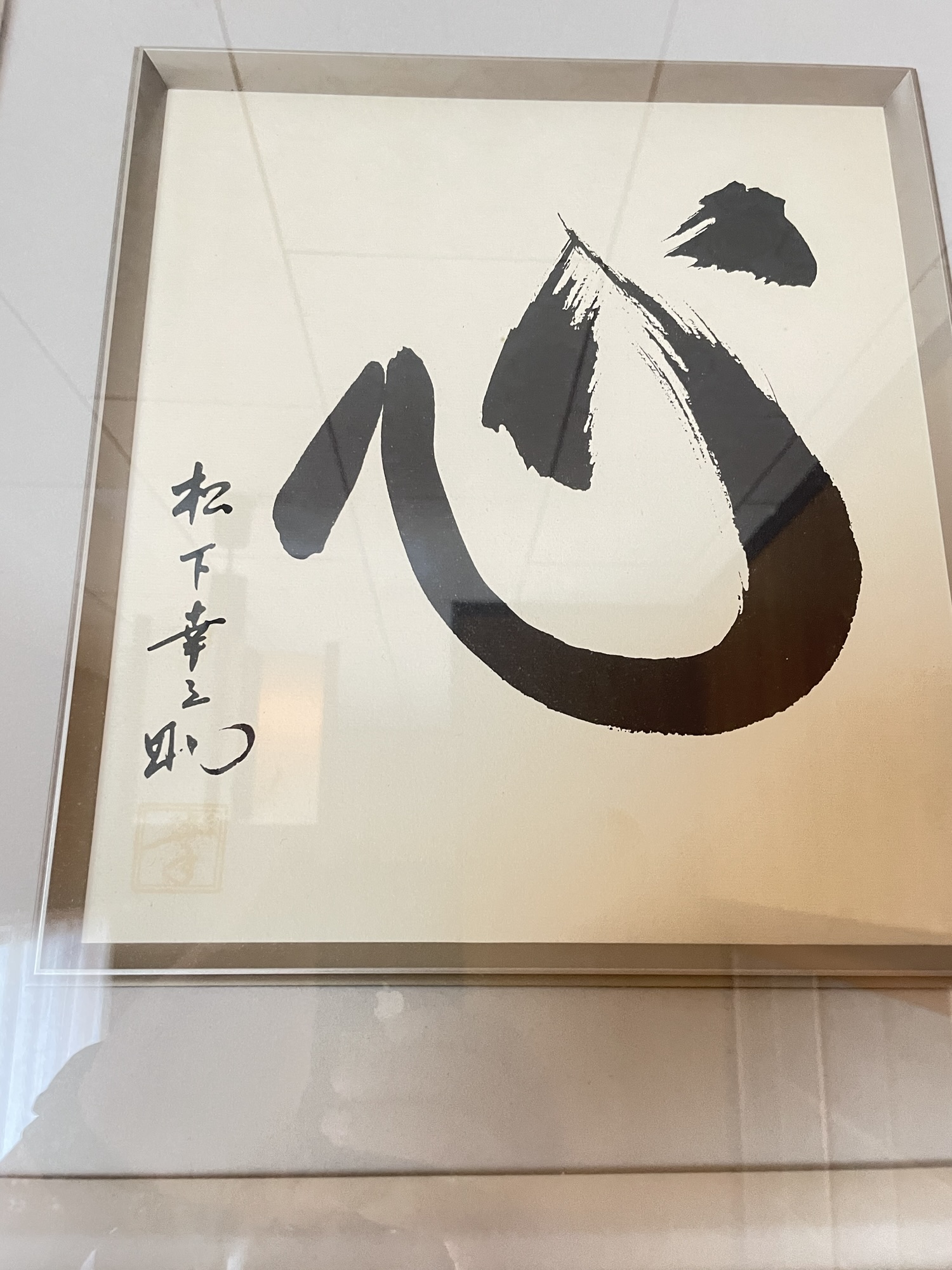
なぜ子供たちの学力が低下しているか
何だか根本的なことらしい
中学生を子どもに持つ、お父さん、お母さん
子どもが中学に上がって、最初の中間テストで「ん・・」ってなりませんでしたか?
うちも、中1を通じて、中間テスト、期末テストで「え、こんなんやったかぁー」ってなってたんよ
それは、何かというと、とにかく自分達が中学生だった時のおぼろげな記憶をたどっても
「こんな点数やったかなーー」
となる点数
息子が必死に「めっちゃ難しい」とアピールするも
それはあなたの準備不足やろ
と、いましめるも、なんかこうぬぐいきれん違和感
平均点が50点とか30点とか
これは息子だけに限らず、みんな難しかったということで
よくよく話を聞いて見ると
授業やってない問題が出たり
先生がさらーーーって授業進めて、なんかよーわからんまま単元が進んでいくようで
とりあえず塾を探すという行動をせざるを得ない
我々、親としては、
「これが中学か、小学校までは児童やったけど、中学からは生徒やから、その違いか」
「これからピリッとして行かなあかん」
という洗礼のように捉えて
一様にビビり、焦り
とりあえず塾を探すという行動をせざるを得ない
のですが
どうやら、自分達が中学の時とは、全く様子が違うので
親の過去の体験は全く役にたたんのでは
ということを感じてたんよね
僕らが中学の時って
初代詰め込み教育、管理主義教育
って呼ばれ、特に僕は神戸やったから、全国でも有名な「中坊は全員強制丸刈り」で
先生は力でねじ伏せ、僕らは知恵でやり返すという
エキサイティングな時代
でも、当時の先生はそれぞれに、程度の差はあったけど
「授業分からん子」に対し、「自分が何とかせなあかん」という行動があって、今思えば、先生はいわゆる、勤務時間外で、自分の時間を使って放課後や、休みの日に補習をしてくれたり
手書きで藁半紙に刷ったプリントを準備してくれてたんやね
部活動もたくさんあって、テキトーに時間潰す部活はなかったので、先生も休日や休み期間も参加してて
先生の人生そのものを、我々に捧げてくれていたように、今になって思うのです
テスト問題も、先生の手書きで、テスト前はどうやったら今回のテストで点が取れるか教えてくれて、平均点が60点を下回ることはなかったような
クラス全体の平均点をどうやったら上げれるか
みたいなところに、先生がフォーカスしていた気がするのです
その、詰め込み教育と管理主義教育の揺れもどしで
正反対の「ゆとり教育」になり
また、それの揺れもどしの「脱ゆとり教育」に2011年から変わって現在に至るのですが(教育指導要領で決まるからね)
「脱ゆとり」の結果、以前の「詰め込み」より「さらに詰め込み」になり
かつ
ゆとりで導入された週休2日のまま
先生は「働き方改革」で「残業しません、定時に帰ります、休日出勤しません」
なので、
「授業についていけない子」「分からない子」を、ケアする物理的な仕組みがない中
僕らの時代に高校でやっていたことを中学でやる
という詰め込みっぷりの皺寄せを
今、子どもたちが一身に受けている状態にあるのですね
学校は「先生と、関係する大人ファースト」状態で、子どもたちは完全に置いてけぼりになっている
こんな状態にある子どもの「テストの点数」に対し
全ての「その子」に求めるのは
かなり酷な状態になっちゃってるんやねー
結果的に
授業についていける2〜3割の子と
ついていけない、多数の子がいて
先生も、文科省の言うとおりやった結果こうなっていて
「学校ではわかるようにならないので、わかるためには塾にいく」
みたいに、中学校の周辺に塾が乱立することで
この状態が、この状況を補完してるって
教育格差が、「塾に行けるかどうか」の経済問題になってしまっているんやね
ここに、現在の文科省の教育指導要領を貼っておきます
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.htm
「生きる力、学ぶ力のその先へ」
それをどうやっていくのか
理念と
それを実行する
物理的な土台が
なんか、丸投げやったり、仕組みがなかったり
どうせやるんやったら、それに関わる人の時間がもったいない
やれば、やるほど、子どもが苦しむことを
自分の仕事としてやらざるを得ない人の、それに携わった人生の時間は
二度と戻ってこないんやからね
という
大人の「自分のことしか考えていない」茶番の結果
君らに、苦労を掛けていることを
それを認めてしまっている大人の一員として
申し訳ない
と
テスト勉強に追われる息子に
まず謝っているのです
「本当の勉強は、学校を卒業してからやからね」
と、苦し紛れに言うしか、今できないのやけど